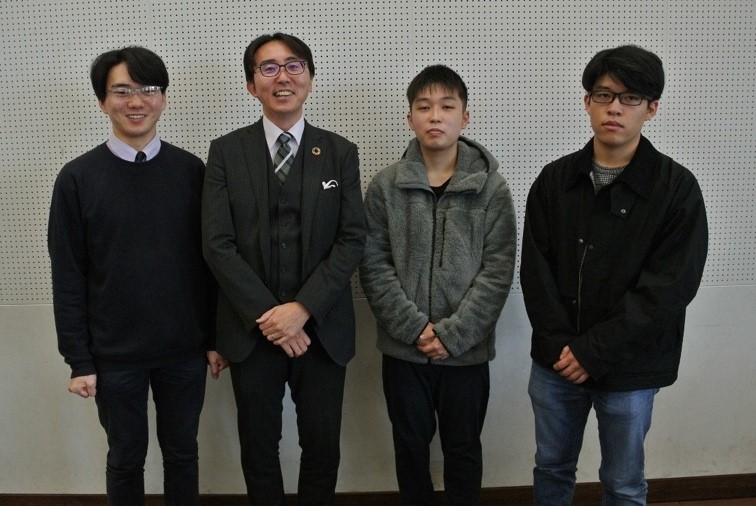~北九州市立大学ひびきのキャンパスの学生が、北九州市を拠点に活躍されている企業様にインタビューを行い、企業の事業内容や魅力をまとめた取材記事を作成しました~
✨私たちが取材しました📝✨
【話し手📢】環境テクノス株式会社 代表取締役社長 鶴田 直さん
【聞き手🎤】北九州市立大学 国際環境工学部3年:I・Yさん、K・Rさん、T・Rさん
✨企業プロフィール🏢✨
環境テクノス株式会社(所在地:北九州市戸畑区中原新町2−4)は、1973年当時、激甚な公害問題に市民や企業、行政が悩まされていた北九州市において、創業者の「世のため人のために」という信念のもとに創業された会社です。2023年12月には創業から50年を迎え、創業時から続く環境測定・分析業をはじめ、環境調査や環境アセスメント、環境に関する課題解決や苦情対応などのコンサルタントなど社会の変化に対応し、常に環境分野において人々の役に立つことを使命として事業を展開しています。一言に環境に関する課題といっても、公害問題からはじまり、廃棄物や生物多様性、地球温暖化など色々と形を変えながら、今では世界的な課題となっています。


【質問1】環境問題や環境コンサルタントに取り組むときに重要なことはなんでしょうか?
企業からの要望に応えるための情報力です。企業が相談する契機の一つとして法律があります。会社の規模や業種などにより守るべき法律の種類が変わってきます。例えば工場からの排水の場合、水質汚濁防止法に則り水質基準や監督者の配置などが必要になります。また、工場の拡張や閉鎖の場合、土壌汚染対策法に則り土壌の調査を行い、土壌の修復や法律に則った対応をする必要があります。このように企業の状況や課題に対して対応が異なっており、これらすべてに対応するための知識や経験、情報が重要になります。
【質問2】標準試薬を作ろうと考えた経緯について、お話下さいますか?
元々は環境テクノス内部での分析精度管理のために作成したものです。土壌分析を行う際、土により性質(泥、砂など)が異なっている、分析を行う工程が長く複雑であるなどから、分析値に大きな誤差が生じてしまう場合があります。当時はこの誤差が人為的なものか機械・行程的なものか判断する「ものさし」のようなものがなく、分析値の正確性の確保のため自社で標準物質を作成したのが始まりです。その後、2003年に土壌汚染対策法施工により土壌調査と分析のための標準物質へのニーズが高まったことで標準物質を商品として作るようになりました。
【質問3】採用者の中には、院卒や技術的な資格を持った人の採用が多く、学部卒にはハードルが高いように感じるが、採用方針はどのようになっているのでしょうか?
約10年前までは、様々な大学の研究室との連携や共同研究を行う中でその研究室に所属している学生を採用していたため、結果的に院卒の採用が多い傾向にありました。近年は採用方針が変わり院卒だけでなく学部卒や高専、工業高校からの学生の採用も増えており院卒の採用が多い傾向はなくなってきています。また、技術的な資格については入社後に取得する技術者がほとんどで、持っている方がいいが無いからと言ってあまり不安に感じる必要はありません。
【質問4】環境テクノスの強みは、どんなことでしょうか?
環境テクノスの強みは顧客対応力です。特に北九州市域での業務実績や経験が多く、北九州市の条例や施策にも精通しているという、北九州市に根ざした企業という強みがあります。そのため、北九州市で新たな事業を行う場合に、水質汚濁防止法や大気汚染防止法、土壌汚染対策法などの対応を行う際に「何をすべきか」を、知識や経験に基づいてアドバイスすることができます。これにより北九州市で事業を行う企業からの需要が高まり、環境テクノスは様々な企業とのネットワークを広げることができるだけでなく、繋がりのある企業を通じて北九州以外の地域にもネットワークを広げ環境ビジネスの拡大に繋げることができます。
【質問5】これからの会社の展開方針・野望として、どんなことがございますか?
環境コンサルとして仕事をする上で、まだまだ対応しきれていない専門分野があります。そういった分野の知識やデータを収集して、より多様な顧客に対応していきたいです。
✨学生インタビュワーの編集後記 ~お話をお伺いした感想~✨
一つに環境問題と言っても、顧客によってその”環境”が異なるからこそ一般な環境問題に対して知識や技術があっても、対応することが困難な場合があることを学びました。
私が大学で専攻している分野を発揮する職種に就職した場合、どのような業務内容を経験するのか学ぶ機会となりました。今回の内容をもとに大学での学びの専門性を深めていきたいです。